
ねぇ、アヤヤ。やっと過ごしやすい季節になったね!



ホントね。今年は格別暑かったからこの涼しさはホッとするよね。



せっかく動けるようになったから…「今の季節だからできること」を教えて



OK。じゃ、とっておきの「秋にしたいこと」教えちゃうね
秋の役割
秋——————
読書の秋、食欲の秋、いろいろありますが。
アヤヤはもちろん食欲の秋です。
夏の間に浴びた強い紫外線、冷房による冷え、そして知らず知らずのうちにたまった疲れ。
それを体がゆっくり修復し始めるのがこの季節。
秋は、心と体が“回復モード”に入る季節です。
自然を見ても、木々は葉を落とし、動物たちは冬に向けて栄養を蓄えます。
外に向かっていたエネルギーが内へ戻る——それが秋のリズムです。
人間の体も同じで、東洋医学では秋は「肺」と「大腸」の季節とされます。
呼吸と排出が整うことで、体の中の“めぐり”がスムーズになる。
深い呼吸ができるようになると、心も落ち着いて、眠りも深くなります。
だから秋は、整える力を取り戻すチャンスの季節なんです。
でも残念ながら、現代人の多くは、この自然のリズムにうまく乗り切れていません。
夜遅くまでスマホを見たり、頭は疲れているのに体が緊張したままだったり。
結果として、朝起きてもスッキリしない——そんな“休んだつもり疲れ”を感じている人がとても多いのが現状です。
自然のリズムを取り戻す!
この悪循環をほどく鍵は、呼吸と夜のストレッチ。
(1)まずは夜のストレッチ
夜は本来、回復と成長の時間。副交感神経が優位になり、細胞の修復やホルモン分泌が活発になる時間帯です。
そこに、筋肉をゆるめるストレッチと、深い呼吸を組み合わせることで、眠る前のわずかな時間が“心身の再生タイム”に変わります。
気温が下がると血流が変化し、副交感神経が働きやすくなります。
つまり「リラックスしやすい季節」なんです。
人間の体は夜になると覚醒ホルモンのコルチゾールが下がり、睡眠ホルモンのメラトニンが出てきます。
そこにストレッチを取り入れると、血流が促され、疲労物質が流れやすくなります。
① 肩甲骨ゆるめストレッチ
デスクワークやスマホでこわばった上半身をゆるめ、呼吸を深くする基本の動き。
- 背筋を伸ばして椅子に座り、手のひらを肩にのせる。
- 肘で大きな円を描くように、前から上、後ろ、下とゆっくり10回まわす。
- 反対回しも10回。呼吸は「吸いながら上」「吐きながら下」。
- 背中の中心(肩甲骨の間)が温かくなればOK。
肩甲骨を動かすと、肺の動きがスムーズになり、酸素の取り込み量が増えます。夜に行うと、胸が開いて自然と深呼吸できるようになります。
② 寝ながら腰ゆらしストレッチ
一日の重力で硬くなった腰回りを解放し、睡眠ホルモンの分泌を助けます。
- 仰向けで寝て、両膝を立て、足を肩幅よりやや広めに。
- 両膝をそろえたまま、左右にゆっくり倒す。
- 片側で止めたときに「ふーっ」と長く息を吐く。
- これを左右10往復。腰から背中にかけて温かくなれば成功。
腰回りは副交感神経が集まるポイント。ここをゆるめることで、呼吸が下まで届き、体温がゆっくり下がって眠りの準備が整います。
③ 背中呼吸ストレッチ
呼吸を深める“究極のリラックス姿勢”。背中をふくらませることで自律神経が整います。
- 四つんばいになり、手と膝を肩幅に開く。
- 鼻から息を吸いながら、背中を丸めて天井へ持ち上げる。
- 口をすぼめて「スーッ」と吐きながら、背中をゆるめて戻す。
- 5〜8回ゆっくり。吐く息を長くするほど効果的。
(2)呼吸を意識
呼吸は、体と心をつなぐスイッチです。
深く穏やかな呼吸をすると、副交感神経が優位になり、脳が「安心していい」と判断します。
すると心拍数が落ち、血圧が安定し、筋肉のこわばりが自然とほどけていきます。
浅い呼吸ではこのスイッチが入らず、体はずっと“緊張モード”のまま。
だから、夜に深い呼吸を意識することが、翌朝の疲労回復に直結するのです。
① 吐くを長くする「リラックス呼吸」
副交感神経を優位にして、体を“休むモード”へ切り替える基本呼吸。
- 背もたれのある椅子に深く座るか、ベッドの上であぐら姿勢になる。
- 鼻から4秒かけて吸う。お腹ではなく、みぞおちの下あたりをふくらませる。
- 口をすぼめて、6〜8秒かけて「スーッ」と吐く。
- この「吸う4・吐く8」を1分ほど続ける。
息を長く吐くことで、心拍数が落ち着き、脳が“もう戦わなくていい”と判断します。
ストレッチの前後にこの呼吸を取り入れると、筋肉のこわばりがほどけ、眠気が自然に訪れます。
② 鼻で整える「深層呼吸」
呼吸を“胸”ではなく“背中とわき腹”で感じる、深い酸素循環をつくる呼吸。
- 背筋を伸ばして、両手をわき腹に当てる。
- 鼻からゆっくり息を吸い、指先が軽く押されるくらい、横と背中をふくらませる。
- 吐くときは、空気が下腹から静かに抜けていくイメージで6秒以上。
- 5〜10呼吸、呼吸の広がりを感じながら行う。
横隔膜(呼吸のメイン筋肉)と骨盤底筋が連動して動き、自律神経の振れを整えます。
この呼吸ができると、体の“芯”が温まり、睡眠中の体温リズムも安定します。
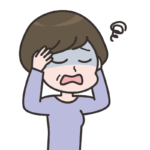
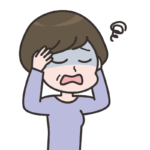
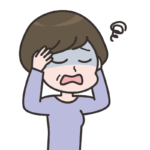
ストレッチと呼吸が大切なことはわかったよ。
でも、ほんとごめんね。
もっと簡単にできないかな・・・



そーかー、、、ダメか笑。
なんとなく説明してて、そんな気がしたよw
というわけで、もっと簡単に新習慣!
ストレッチも呼吸も大切なことはわかっている。
でも、そんな毎日やってられない!
わかる、、、わかります。
そんなあなたにこんな提案。
アロマを使う。
あ、アロマか・・・
そんな風に思ったあなた! 間違ってます。
アロマを軽んじてはいけませんよ。
日本ではアロマは100円均一で売られるほど乱れた業界になっていますが、
欧州など、特にフランスには代替医療として使われています。
国家資格もあるんですよ。
その中で、今回は眠りのアロマ。
アロマは嗅覚を通じて脳に“リラックス信号”が届き、眠りの質が上がります。
香りには感情を整える力があります。
ラベンダーは神経の緊張をやわらげ、スイートオレンジは心を前向きに。
ゼラニウムはホルモンバランスを整える働きがあります。
と言うわけで、アロマ。
アヤヤのおすすめです。
まとめ



アロマを焚きながら、ストレッチの①だけをしたんだけど、
びっくりするくらい眠りが深くなったの!



アロマ、いいでしょう!
スイッチを押して炊いておくだけだから簡単だしね
寝る30分前に照明を少し落として、アロマのスイッチを入れる。
スイートオレンジやゼラニウムの香りに癒されながら、少しだけ肩や背中をゆっくり伸ばすだけ。
それだけで、固まっていた体がじんわり温まっていくのがわかる。
最初は「なんとなく気持ちいい」くらいだったけど、一週間も続けると朝の目覚めが全然違う。
頭が軽くて、1日の始まりが明るくなる。
香りって、本当に不思議です。
ゼラニウムを焚いた夜は心が整うし、深呼吸するたびに胸がふわっと軽くなる。
ストレッチだけだとどうしても“伸ばすこと”に集中しちゃうけど、香りを加えると“ゆるめる”ほうに意識が向く。
体を労わる気持ちが自然に生まれてきます。
夜のストレッチは、今日一日頑張った自分をほめる時間。
私はよく「今日もありがとう」って体に声をかけるんだけど、不思議と肩の力が抜けていく。
ヨガの先生が言ってたの、「体は責めるより、いたわるほうが回復が早い」って。まさにその通りだと思う。
アロマって単なるリラックスツールじゃなくて、“自分の内側と対話するスイッチ”みたいなもの。
夜の静けさと香りが合わさると、自然と呼吸が深くなる。テレビもスマホもオフにして、5分だけでもいいから、自分の体の声を聞く時間をつくる。それだけで、1日の終わりが穏やかになる。
続けていると、心のリセットも早くなる。
嫌なことがあっても、夜ストレッチで“今日を終わらせる”と決めると、翌朝に引きずらなくなる。
寝つきも早くなって、夢も穏やか。香りと呼吸がセットになると、体も心もちゃんと“休む準備”を始めてくれるんです。
夜のストレッチとアロマの習慣は、単なる“癒し”ではありません。
これは、自分を回復させるための静かな儀式。
忙しい日々の中で、私たちは知らないうちに頑張りすぎています。
ストレスを感じたとき、人はつい“何かを足そう”とするけれど、本当に必要なのは“余白をつくること”。
アロマを焚き、呼吸を整えながら体をゆるめる時間は、その余白を取り戻す最もシンプルな方法なんです。
夜に体をほぐすと、筋肉だけでなく思考もやわらぎます。
頭の中で絡まっていた悩みがほどけて、明日もまた頑張ってみようという気持ちが自然に湧いてくる。
それは、体の循環が整い、脳に酸素が行き渡るからこそ生まれる感覚。
季節がめぐり、冬が訪れても、この夜の習慣を続けていれば、春にはきっと、あなたの中に軽やかさが戻っているはず。
鏡の中の自分が少し優しい表情になっていて、朝の空気を吸い込むだけで前向きになれる。
そんな変化を春の光の中で感じてほしいな、と願いをこめて。
すべては、今夜の5分から始まります。
香りを焚き、ゆっくり体をゆるめる。
そのたったひとつの行動が、あなたの回復力を呼び覚ます。



コメント